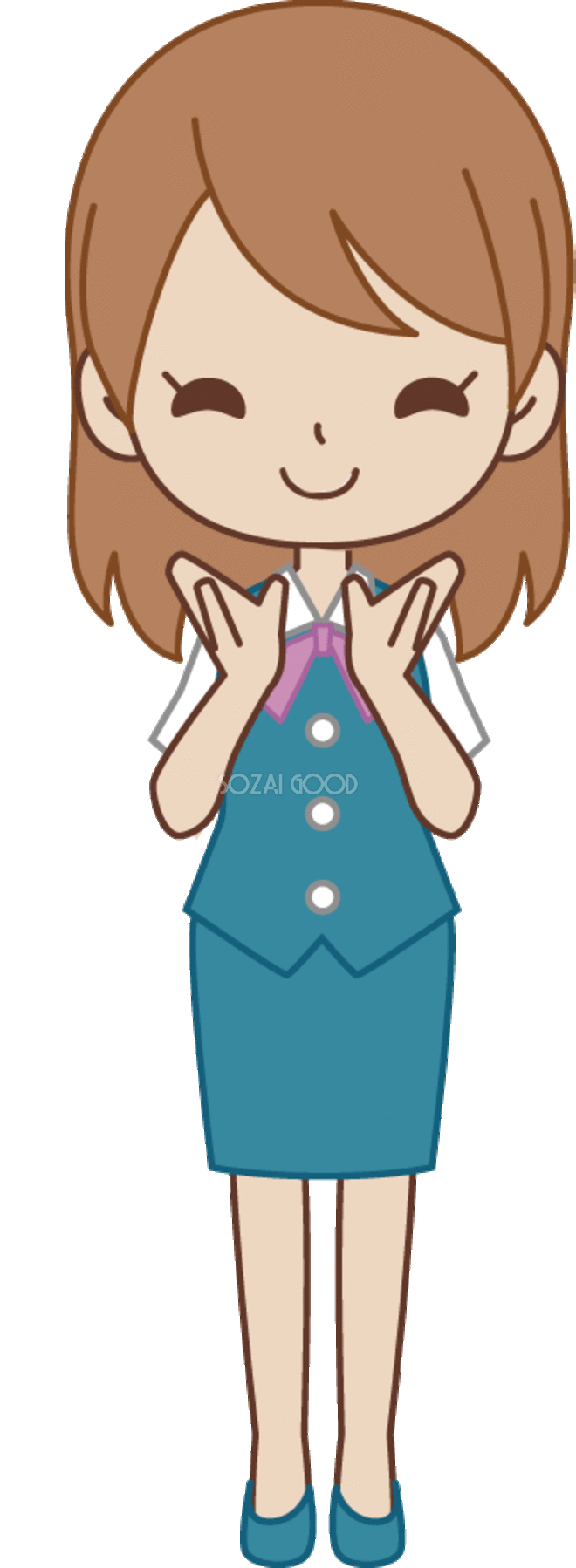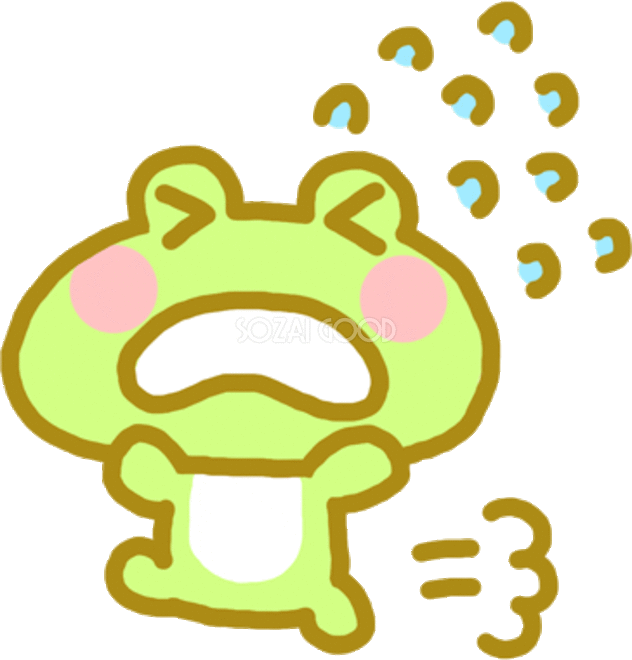さくら変奏曲(只今限定公開版)
桜の季節になりました。
サクラ変奏曲は、まだ仮卒業といったところです。
まだ、暗譜も完璧に覚えていませんので、所々楽譜に頼っています。
苦手としている最大の難関はトレモロです。
少し遅いトレモロですが、少しは上達したと思います。
これで、強弱などの変化が付けられるようになれば、占めたもの!
細部については、今少し練習して、美しい「さくら」のイメージが作れればと・・
願っています。追々練習ですね。
日本古謡として歌われてきた桜は、今もって愛される名曲です。
![]() 弥生の空に見渡す限り さくらさくら花盛り
弥生の空に見渡す限り さくらさくら花盛り![]()
と歌われる歌詞は・・
・・優美で豪華絢爛な花です。
日本全国に桜の名所はいっぱい有りますね。世界からも日本の桜は美しいと大評判。
客を装って店が賑わって見せかける役割を「サクラ」と言うが、
この語源は「桜が咲くと人が集まる」「桜のように、パッと現れ、パッと消える」
演劇や芝居などの内通者をタダで入場させることから、
タダで見られる桜と掛けて「サクラ」となった解釈があるようです。
昔は駅前の路上で、見世物露店商に「サクラ」を使って、
それに釣られて「物を買う」なんて光景をよく見かけましたね。
これもサクラが現れ、パッと客が集まり、売るだけ売りまくってパッと消えます。
桜が満開に咲く、花見シーズンは大勢の人が花見をタダで楽しめます。
今年も素敵な花見を計画して、賑わってください。
さて、ギターで弾く「さくら変奏曲」
この桜変奏曲は田部井辰雄編の作品です。
CDーfontec:FOCD9309
タイトル:シャコンヌ~5曲目に「さくら変奏曲」が収録されています。
テーマ:楽譜の冒頭はオクターブの重音で奏でられます。
ここは、私の解釈で話すと、古来から歌われる
童謡「さくら」を歌ったイメージです。
単純ですが、口ずさみながら、歌ってみたくなるところです。
以前、出版された楽譜「ギターワールドVol.1」に書かれた楽譜は、
イントロの入った楽譜になっています。
ここでの動画は、初めからテーマで弾かれてます。
Var.1は、細かい動きのアルペジオによる伴奏変奏です。
ここは、アルペジオは難しくて弾けない為、原譜を少し変えて演奏しました。
Var.2は、伴音がメロディックな対位声部になる伴奏変奏。
私のイメージを想像するなら、何か思いふける昔に慕った感じの処ではないか。
Var.3は左手のリガート奏法です。
ギター的でウキウキ気分になります。
私のイメージで考えると、満開に咲いた桜を、
花見客で賑わって満足げに、綺麗に咲いた桜を楽しく鑑賞している場面ではないか。
Var.4は旋律の音型変奏とある。
私のイメージですと、花びらが少しづつ散ってゆき、
桜の木の下で、美しい舞が披露されている雰囲気に思えます。
この変奏は、少しアレンジされた、イントロで用いた別のCDにあります。
CDーfontec:FOCD3307
タイトル:ギターと筝~6曲目に「さくら変奏曲」が収録されてます。
Var.5は筝的なリズムによる重音奏法です。
軽快なリズムで花見の最高の盛り上がりの処ですね。
お祭りで、お酒を飲んで盛り上がり、ドンチャン、ガヤガヤと最高の場面ですね。
Var.6はトレモロ奏法です。
私の想像するイメージは、夜桜も終わり、翌日の静まり返った、花見の後・・
桜の花弁は風になびいて散り去る様子が見えてきます。
ここにファンタジー的なトレモロがピッタリ合いますね。
そして、フィナーレは激しいアルペジオで幕〆。
横尾編のさくら変奏曲も素敵ですが、
また違った面白さを楽しめる、田部井編のさくら変奏曲です。
ま~ぁ、プロの様には弾けませんが、何とか仮卒業できました。
せめて、雰囲気を少しでも作る為、花見の様子を撮影した画像を挿入致しました。





 本当に御免なさい。もう1回だけ我慢して聴いて下さいね。・・
本当に御免なさい。もう1回だけ我慢して聴いて下さいね。・・